史学班 小原亨
1.宮川内谷川
(1)暴れ川
宮川内谷川は、阿讃山脈の柄鎌(標高660m・土成町御所)に源を発し吉野川の北岸平野を貫流して旧吉野川に注いでいる。
この川は、山地を離れて平地に出る御所付近では川幅が22mもあるのに下流では全く溝程度の幅しかないという尻無川、即ち天井川であった。このため、古来より毎年氾濫を繰り返し稲や畑作物に被害をもたらし流域住民は洪水との戦いに明け暮れた歴史をたどっている。

宮川内谷川の災害記録によると、宮川内谷川と泉谷川が合流する上板町仁界部落の災害は最もひどい。洪水のたびに家は浸水、畑作物は大被害とあって土地を捨てて離村する人が増え、昭和26年には22戸、その後も家や田畑を売り払って他村へ移住し昭和30年にはわずか13戸に減少している。
土地を捨てた1人である佐々木賢市氏が「私が20代の頃、仁界部落は季節を問わず年に7〜8回も宮川内谷川の氾濫で浸水、そのたび住民は、船やイカダを組んで高台の部落まで飲み水や握り飯をもらいに行ったものです。昭和30年までは、それでもなんとか頑張ったのですが………もう水との戦いに精魂つき果てました。」と住みなれた土地を捨てた悲しみを語っている。
この宮川内谷川の治水対策は、流域の村々の死活の問題でもあった。
『宮川内谷川沿革略史』(上板治水会編)によると、洪水の災害を防ぐための、堤防の築造、あるいは流路の変更など、川の改修をめざした地域住民の運動がようやく明治10年頃から始まっている。関係各村の村長は、手弁当を持ち、わらじばきで県庁へ改修の陳情を繰り返している。しかしながら、小河川にかかわらず改修費が多くかかること、上・下流住民の利害の対立などと関係して住民の願いも容易に受け入れられず見るべき改修も行なわれないまま時が過ぎた。運動を始めて、ゆうに60年という歳月の流れた昭和17年に至って、ようやく第1期改修工事が開始された。この改修は、宮川内谷川から下流の河道の整備に重点をおいた工事で100万円近い財源を投じて行なわれたが、この改修によって洪水が完全に防げることはなかった。
昭和28年9月の13号台風・昭和29年の12号台風では、堤防が決壊し吉野・一条・高志地域に甚大な被害をもたらした。この災害を契機として流域住民は、本格的な治水対策を望む気運が高まり、昭和30年、中小河川改修事業として宮川内谷橋から旧吉野川合流点に至る11kmの区間について総事業費5億2千万円をもって工事に着手した。
続いて、昭和36年10月に徳島県営事業として6億3千万円の費用を投じて、宮川内ダムに着工、昭和39年5月に完成を見た。

宮川内ダムの規模は、集水面積23.14平方キロメートル、重力式コンクリートダムで高さ31.5m、堤長176m、総貯水量135万立方メートルであり、このダム完成により治水の面で、また農業用水(かんがい)確保のうえで流域の村々に大きな役割を果たしている。
ここに初めて、荒れ川が解消し流域住民の永年の悲願が1世紀の歳月を経てようやく達成をみたのである。今は、宮川内谷川流域の板野、上板、土成地方が県北の畑作農業地帯の中核地としての躍進を遂げている。
2 樵木と山柴かせぎ
(1)馬と林業
土成町の山林面積は約4千平方メートルと言われ、その65%が宮川内谷川流域に集まっている。この流域の樹林は、松・杉・桧の針葉樹と樫・馬目樫・こなら等の濶葉樹が繁茂しており流域住民は山林業に従事した。山仕事のことを「山柴かせぎ」と呼び、松・杉の建築用材・樵木材(燃料用の薪)・木炭・手くら(瓦製造用の松の枝)などを生産し生計を維持してきた。

藩政以降、昭和初期までの山柴稼ぎにとって最大の関心事は林産物の搬出、輸送手段にあった。当時の搬出手段としては、人の肩か馬の背に頼る以外に方法はなかった。従って、馬1頭の積載能力は、約40貫程度であるが陸路の完備していなかった山地に於ては馬が最大の輸送機関として盛んに利用された。なお、宮川内谷川流域に、野神社の建立、馬頭観音の建立が数多く見られるのも林業生産にとって欠かすことの出来なかった馬の労力に対する杣人の感謝のあらわれと見てよい。(野神社・馬頭観音については紙面の都合で割愛する。)
(2)樵木(こりき)樵木と木炭
馬によって搬出された林産物のなかで主要なものは、樵木と木炭であった。
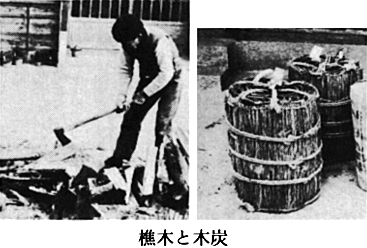
◎ 樵木(こりき)
樵木とは、家庭の燃料用の割木のことで阿波全域で生産され樵木と呼ばれていた。
宮川内谷川流域(御所の樵木)の樵木は、松材を長さ1尺7寸(約56cm)に切りこれを割木としたもので、特色は、松材を使用した。この樵木を高さ3尺2寸5分(1.07m)長さ1丈3尺(4.29m)に棚積みした材量を「1升」と称して商人に売り渡した。資料によると、大正6年代の1升の平均価格は、3円50銭、搬出運送費に2円を要している。この樵木の運搬の主役が馬であった。この馬による搬出とともに宮川内谷川べりの山地の樵木は水流を利用して搬出された。これを樵木流しと呼んでいる。
◎ 樵木流し
樵木流しは、冬から春にかけて山元で伐り倒しておき夏の増水期に川に投げ入れ、「藤原の土場(止場)」(現在の御所小学校東南の位置)まで流下させ、ここで陸揚げして、馬の背によって「二条の浜」(旧柿原村の■船(ひらだぶね)の港津)まで運送された。これより、帆掛の■船によって吉野川を下り徳島の城下や撫養の港に積み出された。

樵木流しにあたっては、順調に流れず途中で岩や岸にかかるため適当な箇所に人夫がいてこうした木材を押し流す作業が行なわれた。また樵木流しをする時は生産者がそれぞれ勝手に流すと他の生産者のものと混って区別がつかなくなる為、流す順序を決めたり、同時に2か所以上流す場合は、土場で流下した量により比例配分をしたりするなどして流送の混乱を防いだ。土場に陸揚げされる樵木は、流下した量材の8割程度の歩止まりで2割は流失してしまうのが常である。
この樵木流しを、海部川では「ボサ流し」と呼び陸路が整備される大正時代まで盛んに流送され河口の鞆の港(海部町)に陸揚げされた。樵木材の材質は、宮川内谷川の松材とは逆に広葉樹の普通、海部地方では、黒木と呼ばれる(エノキ・サカキ・クリ・シイ等)樹木が使われた。大きさは、直径2寸〜2尺位までの木を長さ2尺2寸(約73cm)に玉切りしたものを樵木(ボサ)と呼ぶ。海部川を流した筏とボサ流しは海部の風物詩であった。樫の木は、「シモリ木」と呼ばれ、樵木材には使われなかった。木炭の材料として重宝された樹木であった。
◎ 土場(止場)
普通、コリキ止場と言われるもので上流より流下された樵木を、ここにおいて集材する場所をいう。
構造は、止場となる川の位置に木材3本で三角杭を作り河中に1列に並べ、水位よりわずか高い程度の竹の巣を張りめぐらして樵木が下流に流れないようにしてある。
この止場は、図面のようにA・Bの2段に作り、Aの止場は短くBの止場は長くしてある。
川幅一杯に1つの止場を作ると、水勢と集材されたコリキ材の量によって止場がこわれる心配があるので2段式の止場が考案されてきた。また、高瀬船や漁船の航行が不可能になることを考慮したものである。


◎ 木炭
宮川内谷川流域は、木炭に適した樹木(樫・馬目樫・コナラ等)に恵まれていたこともあって藩政初期から木炭製造が盛んに行なわれて来た。
樹齢が、20年前後に達したものを伐採し、1.8mの長さに切って原料とした。
木炭には、叩けばチンチンと金属音の出る、「白炭」(火力が強く火持ちが良いので家庭燃料以外に蚕室の暖房用、蒲鉾焼用として使われた1級品。)「黒炭」(白炭より柔かく火付もよい。また製炭も容易であり大量に焼くことができた)「松炭」(原料は松材。白炭、黒炭より火付がよく火力が強いので鍛冶屋になくてはならない炭で「かじや炭」とも言われた。)以上3種の木炭が生産されていた。山元で生産された木炭は、炭俵に(白炭1俵4貫8百匁・黒炭・松炭4貫目)詰めて仕上げ、馬の背によって樵木と同様「二条の浜」まで運び出しこれより■船によって「徳島の城下や撫養の港」に送り阪神方面にも積み出された。

◎ 手くら
建築用材や樵木材として伐り倒された松の枝木を松葉のついたまま、約5〜6貫目(約20kg)に束ねたものを「手くら」とこの地域では呼んでいる。
この手くらは、瓦製造の燃料として重宝がられた。また炭焼きで残された小枝を家庭の燃料用薪として、山を持たぬ吉野川流域の一条、柿島、柿原、高瀬の村々の住民が宮川内谷に入山し馬によって運び出した。冬の農閑期が来ると薪を求めて山に向かう村人で賑いをみせたものである。
3.樵木歌とおっかけ節
樵木流しをする時、威勢をつけるという意味で杣人が歌にあわせて作業に従事した。その樵木流し歌が残っている。
◆ 御所の谷から藤原土場へ、流す樵木は多けれど
渕や堰土に阻まれて、土場入りするのは何時のこと。
忠平はん、土場は確かなか、竹はん、留めが破(ば)りつくぞ。
弥一っあん、しぶりをぬきなされ。若い衆、扉門を頼むぞよ。
六っさん右へ、文平はん左へ、樵木を拾い除け、拾い除け。
この歌でみるように、樵木流しの状況、土場での樵木を陸揚げする状況などが手にとるように知ることができる。
また、江戸時代から明治の頃に歌われたものに、「おっかけ節」がある。この、おっかけ節は、村の生活や労働、風俗風習を歌詞に即興的に表現したものである。
何時の頃に歌われたものか不明であるが、宮川内谷川の樵木流しの状況を知る歌詞が残っている。
◆ 御所の谷から、藤原土場へ、流すコリ木は松ばかり。
4.御所のたらいうどんと山柴かせぎ
宮川内ダムが作られ満々とたたえられた湖水に映える山の景観美と渓谷美は、御所のたらいうどんとともに観光客の足を楽しませる。


御所のたらいうどんについて、浅野毎正(つねまき)氏(宮川内字神山、大正15年生)が、次のように話してくれた。「昭和39年宮川内ダムが完成し四季の美と人工の美が加わり観光地としてクローズアップされるとともに、御所のたらいうどんが一躍脚光を浴び観光の顔となってしもうた。元来、たらいうどんは、宮川内谷住民の常食として各家庭で作られていた。この地域は大部分が山地で田畑の面積は狭く雨量も少なく稲作栽培は限定され、小麦を主とした畑作物が住民の主食とされた。たらいうどんは宮川内谷の大切な主食のひとつであった。こうした関係で、御所の住民は、小麦を自作し1年分のうどんを作るのに必要な小麦粉を確保したのである。大体どの家でも、2石〜3石の小麦を粉屋(宮川内谷川の谷水を利用して水車を回し小麦粉を製造する。水車で製粉することから「くるまや」とも呼ばれた。)に納め小麦粉を作った。宮川内谷川流域には、6軒の粉屋があって部落の全家庭の小麦製粉を引き受けていた。たらいうどんは、田植えの終った田休みとか、節供の遊山がわり、親類縁者の来訪時等に軽い馳走としても振舞われた。」


御所のたらいうどんは、もともとは山柴かせぎ人夫(材木伐出し・樵木・木炭の労働)の仕事納めの振舞いとして、うどんを馳走するのが通例であった。この時、大勢の人夫達に、つぎ分けするのが面到であったので、茄釜を囲んで直接釜から引きあげて食べた。こうした形容から、釜抜千本と呼ばれた。後になり釜から直径1mもある木製の「はんぼう」(飯盆)に入れて食べるようになった。昭和6年に土井通次県知事が視察に来た折に、飯盆に盛られた、うどんを食べて帰った。後になって知事が「たらい」の様な器に入ったどんを食べたが、うまかったという話から「御所のたらいうどん」と呼ばれるようになったと言われている。いずれにせよ、住民の食生活、特に山に生きる杣人の常食として欠かせない食糧であり土地の生産のなかに食生活を求めた自給の体制であった。また、たらいうどんの「ダシ汁」に宮川内谷州でとれた「ジンゾク」の味が一段と淡白な風味を加え、御所うどんを更に有名にした。「ジンゾク」は、ハゼ科の一種で阿では、ゴリ・ヨシノボリ・ドウロクとも呼ばれているが、体長3〜4cm、川のせせらぎの水底の小石の下で生息している。宮川内谷の杣人達が、川でジンゾクを捕えて川原に石のカマドをつき川木(カワギ)を燃料に、うどんをゆで、飯盆に釜抜きうどんを作り、ジンゾクのつけ汁で舌つづみを打ったのであろう。御所のたらいうどんは、宮川内谷川に生きる人々の体験からくる生活の知恵によって作り出された食文化ではなかろうか。
5.生まれ変わる宮川内谷
幾世代を重ね育って来たふる里、風土は村人にとってかけがえのない宝であり誇りでもある。誰人も、ふる里はすばらしいと感じ、ふる里を愛する心に変わりはない。永い時の流れのなかで築きあげた尊い遺産が生きている。
宮川内谷の村人もまた同じであろう。宮川内谷川は、人も知る暴れ川。この川との戦いに生き抜いた。そうして川を治めることができた。昭和39年宮川内ダムが作られ135万立方メートルの湖水が生まれ周辺の山岳美、渓谷美と人工美がうまく調和され、昭和41年に県立自然公園に指定されて一躍観光地として生まれ変わり、常民の常食であった「たらいうどん」が観光の目玉商品となり行楽の客を楽しませてくれる。

一杯500円の御所たらいうどん、宮川内谷川の清流のせせらぎを聞きながらの賞味は、また格別なものがある。御所小唱にも「山は緑で谷川そめて、のぼるジンゾク、その影おって舌うちたのしむ、この風味、御所はよいとこ、名物うどん」と歌われているが、本当に、この地を訪れる人々の旅情を心ゆくまで慰めてくれるのが、御所の村である。