民俗班(徳島民俗学会) 青木幾男
1.はじめに
上郡(かみごおり)とは、吉野川中流、上流にまたがる徳島県美馬郡、三好郡の地域を指し、下郡(しもごおり)は、麻植郡山川町舟戸・阿波郡阿波町岩津から下流の麻植・阿波・板野・名西・名東(現徳島市の一部を含む)の5郡をいう。江戸時代まではそのような呼び方でその地方を表現していたが、政治的にも、経済的にも別に違いがあるわけではない。1本の川を通じて上流と下流があり、上流には山地が多く耕地が少ない。下流は平地が多く、交通の便がよいのは当然の理であり、どこでも同じ現象で、とりたてて上下に分けた理由がわからない。
筆者は20年近くの間、毎年阿波学会調査に参加して、各地の民俗等を調査し、報告してきた。地域毎に地勢、地質、植物、人口、生産物による社会環境の違いがあり、その違いに対処し、隣地とどう協力して社会の有効性を高め、困難を排除するかということで人間社会は成り立っている。そこに政治があり、住民の知恵があり、人情がある。それらの経緯は生活習慣として、その時代時代の生活器材の中に読みとることができる。私たちはそれらの遺物をも調査している。
上郡、下郡は、太平洋に面して、漁業を中心とする那賀、海部両郡の「南方(みなみかた)」に対して「阿波北方(きたがた)7郡」と言い、ともに江戸時代から、阿波藍の生産地として栄えた所であった。上郡は山林が多く、平地が少なく、耕地は傾斜が急だったので階段状の畑地に藍(あい)、煙草(たばこ)を栽培していた。客観的に見て下郡(平地部)に比較して生産力も生活環境も悪いはずのこの山地に張りついてきた要因は何であったか。その結果どんなことが起こったのか。
江戸時代までは封建制政治であって、農民は居住地の役人がどんなに無理を言っても、また生産力がどんなに低くても、勝手にその土地を放棄して、他の土地に移住することができなかった。またそのことを住民が相談していても厳重な処分(死罪)が待っていた。
「大日本農政類編」巻之四法制(1)の中に
「[百十六代]後櫻町天皇、明和七年庚寅四月、幕府制シテ曰ハク、何事ニヨラズ宜シカラザル事、百姓大勢申合セ候ヲ徒黨ト唱ヘ、徒黨シテ強テ願ヒヲ企ツルヲバ強訴ト云フ。
或ハ申合セ村方立退キ候ヲ逃散ト申ス。前々ヨリ御法度ニ候條、右類ノ儀之レアラバ、居村他村ニ限ラズ、早々其ノ筋ノ役所ヘ申出ベシ。御褒美トシテ徒黨の訴人ハ銀百枚、逃散ノ訴人ハ同斷、右ノ通リ之ヲ下サル品ニヨリ帶刀、苗字ヲ御免アルベキ間、假令一旦同類ニ成ルトモ告發スルニ於テハ其ノ科ヲ赦サレ御褒美下サルベシ。村々騒立候節、村内ノ者ヲ差押ヘ、徒黨ニカゝハラズ一人モ差出サゞル村方之レ有ラバ、村吏ニテモ百姓ニテモ、重モニ取静メ候モノハ御褒美銀下サレ、帶刀苗字御免アルベシ差シ續キ静メ候モノモ、若シ之アラバ夫々御褒美下サルベキモノナリ。憲法部類」(句読点は青木)と記されている。
古代はそれ程でもなかったが、中世から武家政治が発展して行く中で、農民は「物質の生産者」としての任務に束縛され、自由も、生きる権利も認められていなかった。中世から近世にかけて、立地的にきわめて生産性の低いと考えられる上郡の人たちは、その中で、どのように対処してきたか。「生涯どんなことがあっても、そこに居住しなければならない運命にある」と考えた時、それに耐える方法が生まれるのは当然である。それを繰り返した長い生活の歴史の中で、「上郡人気質」ともいうべき、従来の生活環境の中で強じんに生きていける気質をつくりあげていたことを知った。
前記疑問については、貞光町・半田町・三好町・井川町、そして今回穴吹町の民具を調査したことで、一応の解答が得られたように思う。この報告は、穴吹町を中心にしながら、上郡全域から代表的事例を挙げて裏づけとする。
2.上郡農民の住民性
「徳島県百科事典」(2)の「かみごおり 上郡」の項で執筆者羽山久男氏は「(この地方は)水利条件に恵まれないため(中略)畑作が中心であった。このため上郡地方の役牛は、讃岐山脈の猪(い)ノ鼻(はな)峠・東山峠(塩入峠)・真鈴峠・三頭越(さんとえごえ)・相栗峠などの峠を越えて讃岐の綾歌・仲多度・三豊3郡の水田地帯に出かせぎさせる習慣が昭和初期まであり、牛が帰ってくるときにはお礼の米を積んで帰るので、上郡では『米牛』、讃岐では『借耕牛(かりごうし)』といった。上郡では藩政時代から商品経済に巻き込まれていたので利にさとく、粘り強い住民性が生まれた」と記し、上郡の住民性を「利にさとく、粘りづよい性格」と評している。「利にさとく」とは、単なる食糧生産では生活ができないので、「借耕牛」の如く流通経済にたよらざるを得なかったことをいうのであろうか、たしかにあてはまることであった。「粘りづよい」とは、沈着で、百姓一揆(いっき)などを避けることができなくなっても工夫をこらし、有利にみちびいた農民の賢明さを指しているのであると思う。それを証明するために、換金作物としての上郡の特産物を挙げ、賢明さを示す例として、上郡一揆を分析してみよう。
1)特産物
上郡の農家は藍と煙草を換金作物として広く栽培していた。品種を改良したのか栽培法を工夫したのか、藍も煙草も地方独特の品質の良さがあり、有利に販売できた。
煙草葉は特に「阿波刻みたばこ」に使われ、肉が厚く、香りが良いので、阪神方面に出荷されて、江戸時代から阿波の特産として知られていた。明治に専売制になってからは、池田に専売局工場が設置されて、近年まで操業しており、時には「煙草景気」に町全体が華やいだこともあった。

藍は阿波北方の特産であるが、上郡産の葉と下郡の葉とは色つやに少し違いがある。美馬・三好など山間高地の葉は「山葉(やまは)」といい、色が濃いが光沢が乏しい。これに対して下郡の葉は「里葉(さとは)」と呼ばれ、色は薄いが光沢がある。山葉、里葉を別々に加工するよりも、混合することによって製品がよくなり、混合の割合によって客の好みの色合いが出せるよう、工夫した。色つやは藍の商品価値であり、阿波藍の評価の基準もその一点にあった。藍師(あいし)(藍商)は代々秘伝の製法を伝えて、独自の売場を持ち、自らも藍を栽培し、不足分は葉藍を買入れて11月から12月にかけて人を雇って藍玉に搗(つ)き、1月ごろまでに仕上げる。混合の方法を簡単に述べると、藍玉搗(あいだまつ)きのはじめに「搗見臼(つきみうす)」「搗見杵(つきみぎね)」という小さな石臼と、長さ20cm
くらいの小さな立杵(たてぎね)があって、山葉と里葉の分量をはかって、臼で搗き、小さなダンゴをつくり、薄い和紙にポンポンと幾つか印鑑の様に押してみる。その和紙を透して藍の色を鑑定する。これを「手板鑑定法(ていたかんていほう)」という。判を押した和紙を「手板」といい、指でつまんだダンゴは椎茸(しいたけ)状になっているので「椎茸」という。椎茸は藍玉商談の時見本となり、手板によって評価をきめる。明治29年(1896)10月発行の「徳島縣藍商繁榮見立」(3)の中から上郡の藍師を書き出して見る(表1)。
その他の特産物として、半田の漆器・漆液・素麺(そうめん)、岩津の火打金(ひうちがね)、山城の漆液・棕梠皮(しゅろかわ)・紙すきがあるが、地域的に遍在し、生産額も低いので省略する。
前掲のように、明和7年(1770)4月幕府は農民の「政治向け訴えの申合せ・強訴(ごうそ)・逃散(ちょうさん)」を禁止したが、それは全国の藩主、藩士の圧制と賦課の過重が争乱の危機を含んでいたためであったが、農民にきびしくするのみで、制度を改める事をしなかったので、かえって時代が進むにつれて、一揆が頻発することになる。
2)上郡一揆
古来百姓一揆の例は全国に少なくないが、そのほとんどが、領主、役人の誅求(ちゅうきゅう)と暴虐(ぼうぎゃく)に耐えかねて、百姓が徒党を組み、暴力をもって領主、役人を襲撃する形式のもので、領主、役人を倒し得てもその首謀者は極刑に処され、多数の連類者が処罰され、しかも百姓の願いは容易に達せられないのが普通であった。そんな中で上郡一揆を代表する例が起きた。天保12年(1841)12月4日夜、山城谷村の百姓631名は峠を越え、蓑笠(みのがさ)を着て雨の降る中を伊予の国(愛媛県)に越境した。それを知った予州宇摩郡上山村では大騒ぎのあと、事情を聞いてようやく安心し、村内の安楽寺に案内した。翌日三島代官所からの指図を受けた妻島村の大庄屋、中川善兵衛は百姓たちを安楽寺の本堂に集め取調べを開始した。農民は阿波藩に対する16項目の要求書をもっており「藩が税増収を目的として計画している漆液の一手買上げ反対、楮(こうぞ)・煙草・蜜蝋(みつろう)・金物・綿実の取扱い、牛馬売買の緩和、隣国と軒を接する国境に住む者が飯料として3升、5升の麦を他国より買入れても没収しないこと」など阿波藩が要求を入れ、処分者を一人も出さないと約束してくれなければ帰らないと訴えた。今治藩主は農民の要求を全面的に支持し、阿波藩に対して「農民の要求は当然と思われるので、全員を処分無く引取るか、さもなくば当藩で農民の頼みを入れ、全員を留め置き領民として処理する」と伝えた。驚いた徳島側は郡代高木真之助・三間勝蔵を現地に派遣して折衝にあたらせ、その間一揆の人たちは、今治藩の村役人たちが相談して安楽寺その他大百姓の家々に分宿させ、食糧は1人1日米3合(1日合計1石8斗3合)総菜として菜や大根の汁、いわし、香の物など時に応じて支給していたが、山城谷と境を接する山村であるから、その混雑ぶりも推察できる。一揆の連中は10日間滞在し、12月14日引き揚げた。
阿波藩の代表として現地に赴いた高木真之助・三間勝蔵は、農民の要求をすべて受け入れ、一揆の農民は自力で国境まで引き揚げたことにして、処分は行わない旨を約束署名した文書をあたえ、全国でもあまり例を見ない、百姓側の大勝利に終わった。この一揆は上郡の代表的一揆と言われており、この一揆を契機として上郡に一揆が続発するのであるが、天保12年のこの一揆だけは「農民の整然とした戦い方」「高木郡代の罪人を一人も出さなかった裁き方」に賞賛が寄せられている。この一揆は一般的に見られるような、感情的、群集心理からくる偶発的一揆ではなくて、慎重に計画され、万全を期した一揆ではなかったかと考えさせるものがある(上郡の文化人と郡代高木真之助の間に俳句等を通じて何等かの交流があったかも知れない)。
3.民具から見る上郡
上郡文化の特徴をつきとめようと考え始めたのは、昭和56年(1981)の貞光町調査からであった。今から17年前、そのころ県内の他の山村では、すでに過疎が進んでいて地域問題として論議されようとしていた時であった。庚申(こうしん)信仰を調査するために、僧地、家賀、川見、長瀬、日浦、吉良、浦山、猿飼など、何日かをかけて全集落を回った時、農家では傾斜地の大部分に栽培されている煙草の生育期で忙しくしていたが、大人も子供も元気で何の不安もない様子で、生まれた集落内で居住し、山の上の分校も活気にあふれていた。農家では家々で自家用のスイカを栽培しており、昼休みなどには見事なスイカを割って、話を聞きに行った私たちに振舞ってくれたのは有難かった。その時からこのパワーはどうして生まれたのかを知りたかった。
1)からうす
平成7年(1995)7月の三好町の調査の際、町中央公民館資料室に1基の「からうす」
(図1)があった(4)。私たちが従来見てきたからうす(図2)とは様式が少し異なっていたので、その後もその様式の広がりを調査していたが、山村部でもすでにからうすの遺物は少なくなっていたため、聞き取り調査で調べてみると、三好町から1,000m
近い峠を越えた香川県仲南町教育委員会の資料室に1基、同型が保管されていた。また徳島県側では池田町、三好町、美馬町、さらに吉野川を渡り、山城町、井川町、半田町から東西祖谷で使用していたことがわかった。この地域は1,000m
の山々でかこまれた地域であったので、仮称としてこれを「峠型」(峠を越えて伝えられた)、図2型を「平地型」(一般的な陸路、船便などによって伝えられた)として分類したが、「峠型」は、仲南町と三好町のもののほかには実物を確認することができなかった。ところが平成10年7月28日の穴吹町の調査で、向井昌利さん(字支納285、74歳)が「からうすの棹(さお)」を大切に保存して居られることを知って驚いた。調べてみるとまぎれもなく峠型であった(図3)。向井さんは「このあたりは皆これであった。これが楽だから使うのだが、平地の人がなぜ『平地型』を使うのか理解できない」と話してくれた。まさに向井さんの言葉の通り、道具は使いやすいから使うのだが、同じ道具を繰り返し使っていると「慣れ」ということもある。長年繰り返して使っていると、それでなければ使えなくなることもある。上郡の「峠型からうす」は上郡の人の気質から来るものかも知れないが、なぜ平地型から峠型に変化していったのか。上郡の人に峠型がなぜ使いやすいのか、まだ解明しなければならないなぞが多く残されているが、「峠型からうす」が阿波上郡の特徴であることに自信を強めたのは、穴吹町調査の成果であった。
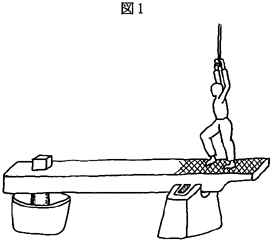
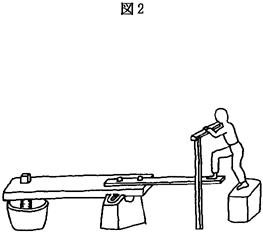

2)土あげ鍬
平成3年(1991)の半田町調査では、いわゆる機械化農業で動力化し、大形化した農機が傾斜地でどう使われているかを調べるために、半田町中熊(なかくま)集落の丸野政信家を訪れた。丸野家は標高545m、家の周囲に約40a
の畑があり、畑の傾斜は30度を超えている。西方は矢筈山(1868m)に続き、地域全体が急傾斜地である。
丸野家で使用する耕作農具は全部で15点、全部1人用手持鍬(くわ)で柄が短く、柄と刃の角度が深い。「この鍬は、紙屋(半田川沿い)の鍛冶屋(かじや)さんが廃業したので、もうできない」とこぼしていた。「小型耕運機を買ったが、まったく使えない」と納屋の隅に置いてあったが、使用する鍬のない傾斜地農業はこれからどうなるのか、と案じながら、鍬の角度を図に書いて報告とした(5)。
穴吹町の調査で、前記向井さん宅の農具置場に10本ちかくの「土あげ鍬」があった。図4のように6本爪(づめ)の丈夫な鍬である。柄に対して刃の角度がきわめて深い。この地域では「逆鍬(さかぐわ)」「逆掘(さかぼり)」とも呼んでいる。山間の畑はそのほとんどが急傾斜地である。そのために畑の表土は自然に低い方に流れ落ちる。向井さんの家の周囲も、30度から40度の傾斜の段々畑であった。どこの家の畑もみな同じような状態なので、旧10〜11月のころ、麦蒔(ま)きの時にこの鍬は活躍する。向井さんの話によると、昼間は、それぞれの家で芋掘り、そばの脱穀などの仕事をしておき、夕食後あらかじめきめられた組内の家に集まってくる。全員、昼間牛ですき起こしておいた畑で横一列に並んで、土あげ鍬を使って山手の方へ土をかき上げるのである。昼間の労働で疲労しきった後の仕事なので、その苦しさは口では表現できない程の厳しさがあったが、皆で一緒に行っているから耐えられたのかも知れない。夜間作業なので作業の照明は乾燥した竹(長さ約3m
の竹を割って、直径10cm
ばかりの束)に点火し、たいまつ代わりにしたものを子供に持たせた。子供も重労働であった。作業時間は2時間から3時間におよんだ。晩秋、旧11月の夜風は身を切るように冷たかったという。山分はどこの地域でも同じころにこの作業をしていたので、向かいの山から見ると、作業の火が深夜に至るまで美しく眺められたという。これを支納では「夜ごなし」「地こなし」とも言った。麦蒔きは、組内の全戸が適期内に行なえるように計画し、夜業時間と順番はそれによって決めて居り、単独で麦蒔きをすることはなかった。この作業は昭和30年(1955)ごろまで穴吹町の山間部でさかんに行われたが、その後は麦も次第に栽培されなくなり、夜ごなしもできる人が居なくなった。夜ごなしは集団で行うから実行できたのかも知れないが、その体力の多くは、習慣として鍛えあげられた体質的なものとなっていたと考える。その体力は今は無い。

4.おわりに
以上、上郡民衆のおかれた立場、そして困難にどう対処したかを述べてきた。それは一人一人の個人的思考から生まれたものではなかった。群衆としての上郡住民は賢明で、質実、勤勉であった。住民はもともと傾斜地を好んで山に住みついたものではなかったが、古代は山の方が食糧が豊富であった。中世から近世にかけて封建制度がきびしくなると、与えられた限界の中で、生きる方法を考えるようになった。上郡の人が封建制をよろこぶはずもないが、封建制が上郡の人を鍛え、錬磨したと言えるかも知れない。山を耕して煙草、そば、藍をつくり、標高数百
m
の山々に村をつくり、江戸後期から明治にかけ岡本韋庵(開拓者)、三宅舞村(医学者)、その他多くの人材を出したのも上郡文化であった。それは、自由とはうらはらに、権力にいじめぬかれた山村の人々のがんばりであったかも知れない。山村の人々は、封建制の中では自らの力で自然に対応できる体質をつくり、山村を支えてきた。それは、封建政治だからほかに方法がなかった、とも言えるかも知れない。
封建制から開放された今、山村の自然を守るものは誰か。村は過疎でさびれ、山林は荒れている。むかしは封建制が住民を縛りつけていた。それが山村を支えてきた。都市中心の政治、人口比率中心の政治では、ますます拡大化する過疎地域で人もなく、仕事もない。
面積だけ広い山をどのようにして守るのか。国家的視野から考えてほしいと望むものである。
参考文献
1.農商務省農務局纂訂(1897)大日本農政類編.農商務省(明治後期産業発達史資料,第279巻 [龍溪書房,1995]に所収).
2.徳島新聞社調査事業局編(1981)徳島県百科事典.徳島新聞社.
3.中山民太郎(1896)徳島縣藍商繁榮見立.中山民太郎
4.青木幾男(1993)「からうす」の構造からみる三好町の文化圏.総合学術調査報告 三好町,郷土研究発表会紀要,39,263.
5.青木幾男(1992)半田町の民具.総合学術調査報告 半田町,郷土研究発表会紀要,38,265.